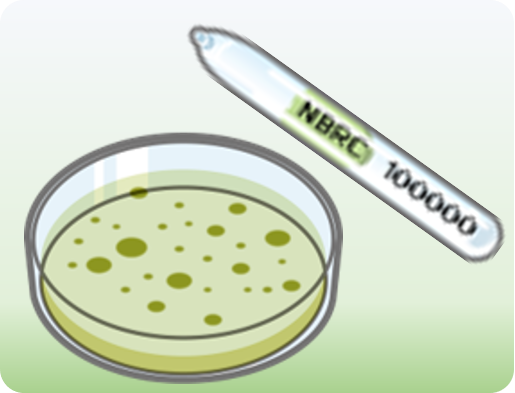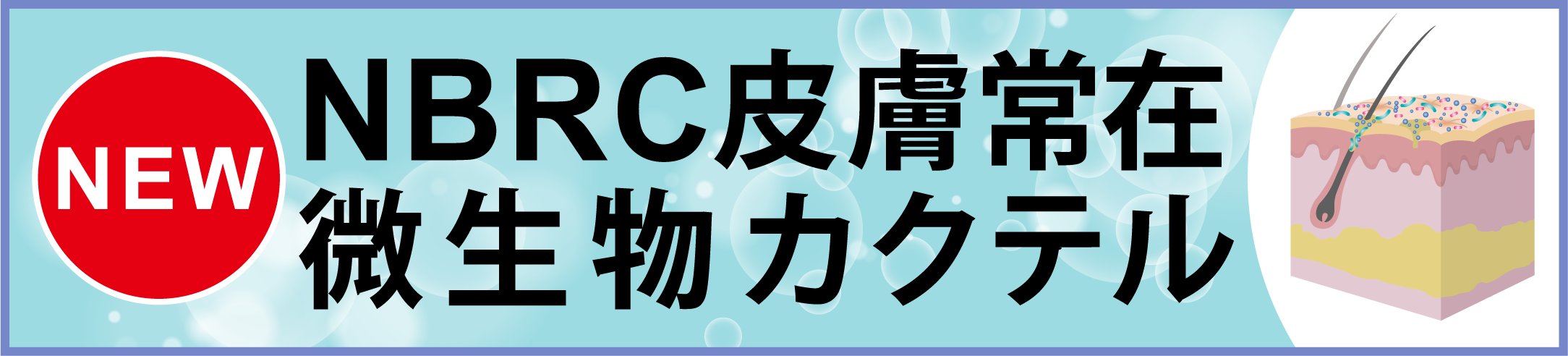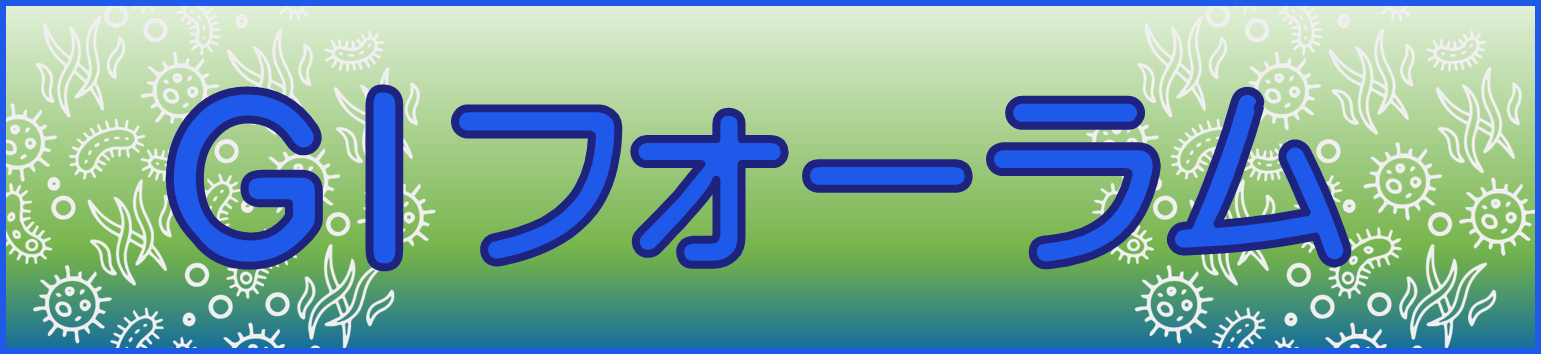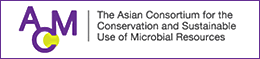NBRCニュース 第95号

今号の内容
1.
新たにご利用可能となった微生物株
糸状菌では、ペットフードから分離された好乾性のXerochrysium xerophilum NBRC 117031を公開しました。保存食に生えるカビの比較参照株としての活用が期待されます。
細菌では、海洋に浸漬したプラスチックフィルムに付着したバイオフィルムから分離した28株(NBRC 117140–117141、117144–117153、117155–117156、117158–117171)を公開しました。生分解性プラスチックPHBHの分解活性を示したAlteromonas sp. NBRC 117144も含まれます。NBRCは、これらの菌株以外にも生分解性プラスチックを分解する微生物を分譲しています。各株の分解活性や関連情報については、「日本沿岸での生分解性プラスチック浸漬試験から得られた微生物とそれらの分解活性」をご覧ください。
また、海生渦鞭毛藻類Karlodinium veneficumから分離されたGymnodinialimonas phycosphaerae NBRC 114899Tを公開しました。
【新たに分譲を開始した微生物資源】
https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/nbrc/new_strain/new_dna.html
【参考】海洋プラスチックごみ問題に対するNITEの取り組み
https://www.nite.go.jp/nbrc/industry/plastic-waste.html
◆RD株
建築資材等に付着したバイオフィルムから分離した微細藻類29株と食品や植物から分離した乳酸菌10株の提供を新たに開始しました。また、きみつ食の彩りプロジェクト「カラー工房(酵母)」において、千葉県君津市特産の花「カラー」から分離した酵母9株の提供を新たに開始しました。
【新たに提供を開始したRD株】
https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/rd/new_rd.html
【提供可能なRD株リスト】
https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/rd/available_rd_list.html
細菌では、海洋に浸漬したプラスチックフィルムに付着したバイオフィルムから分離した28株(NBRC 117140–117141、117144–117153、117155–117156、117158–117171)を公開しました。生分解性プラスチックPHBHの分解活性を示したAlteromonas sp. NBRC 117144も含まれます。NBRCは、これらの菌株以外にも生分解性プラスチックを分解する微生物を分譲しています。各株の分解活性や関連情報については、「日本沿岸での生分解性プラスチック浸漬試験から得られた微生物とそれらの分解活性」をご覧ください。
また、海生渦鞭毛藻類Karlodinium veneficumから分離されたGymnodinialimonas phycosphaerae NBRC 114899Tを公開しました。
【新たに分譲を開始した微生物資源】
https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/nbrc/new_strain/new_dna.html
【参考】海洋プラスチックごみ問題に対するNITEの取り組み
https://www.nite.go.jp/nbrc/industry/plastic-waste.html
◆RD株
建築資材等に付着したバイオフィルムから分離した微細藻類29株と食品や植物から分離した乳酸菌10株の提供を新たに開始しました。また、きみつ食の彩りプロジェクト「カラー工房(酵母)」において、千葉県君津市特産の花「カラー」から分離した酵母9株の提供を新たに開始しました。
【新たに提供を開始したRD株】
https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/rd/new_rd.html
【提供可能なRD株リスト】
https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/rd/available_rd_list.html
2.
びせいぶつ学習帳:知っているようで知らない微生物の話(6)
麹菌の魅力と可能性を探る【後編】
~麹菌だけではない、コウジカビ属菌の魅力~
(齊藤 舜介)

【酵素利用に見るコウジカビ属菌の力】
コウジカビ属菌の最大の強みは「圧倒的な酵素産生能力」です。1894年、高峰譲吉氏はアスペルギルス・オリゼから消化酵素を抽出し、「タカジアスターゼ」と名付けて製剤化しました(1)。これは世界で初めて商業的に成功した酵素製剤であり、酵素産業の出発点とされています。その後も、コウジカビ属菌が生み出すアミラーゼ(デンプン分解酵素)、プロテアーゼ(タンパク質分解酵素)、リパーゼ(脂質分解酵素)、セルラーゼ(セルロース分解酵素)、ペクチナーゼ(ペクチン分解酵素)といった酵素が、食品加工や酒類醸造をはじめ、化学・医薬などの分野でも利用されてきました(2, 3)。
さらに、コウジカビ属菌には「タンパク質を大量に分泌できる」という特徴があります。そのため、外来の酵素をつくらせる「生産工場」としても利用されています。実際に、洗剤用の遺伝子組換えリパーゼがアスペルギルス・オリゼによって実用化された例もあります。
また、コウジカビ属菌の中でも古くから食品づくりに利用されてきた実績のある麹菌の安全性は高く評価されています。米国ではアスペルギルス・オリゼ由来の乾燥菌体や酵素がGRAS(Generally Recognized As Safe)として認められており、国際的にも安全性が裏づけられています。こうした評価は、麹菌や産生する酵素を産業で安心して使うための大きな根拠となっています。
【代謝産物がもたらす新たな価値】
コウジカビ属菌の力は酵素だけにとどまりません。発酵の過程で生じる有機酸、ビタミン、アミノ酸、抗酸化物質などの代謝産物は、食品添加物、医薬品原料、化粧品原料、機能性食品素材などで利用されています。その一つが「コウジ酸」です。1907年に斎藤賢道氏によって蒸米麹から分離され、続いて藪田貞治郎氏によって化学構造が決定されました(4)。その後、肌の美白効果が注目され、現在ではシミやくすみを抑える成分として、国際的に化粧品分野で広く利用されています。
また、「クエン酸」も重要な例です。食品では酸味料や保存料、医薬品では安定剤や錠剤の成形助剤、さらに工業分野では金属イオンのキレート剤として利用され、世界中で年間数百万トン規模が生産される不可欠な物質となっています。クエン酸は現在、主にアスペルギルス・ニガーを用いた発酵によって生産されており、世界の供給量の大部分を占めています。
さらに、コウジカビ属菌に関する代謝研究は、ビタミンB群やグルコン酸などの有機酸の生産へと広がり、酵素だけでなく代謝産物の面でも、私たちの食生活や産業を支えています。
【プラットフォーム微生物としてのコウジカビ属菌】
コウジカビ属菌の可能性をさらに広げたのが、遺伝子研究の進展です。2005年には、我々NITEも参画したアスペルギルス・オリゼのゲノム解読結果が報告されました(5)。その後、ゲノム情報に基づく詳細な解析に加え、ゲノム編集などの新しい分子生物学的手法が導入され、特定の酵素の大量生産、新規物質の創出や代謝経路改変といった研究が本格的に進められるようになりました。
いまや、コウジカビ属菌は、合成生物学や代謝工学の「プラットフォーム微生物」として、より効率的な産業プロセスの開発や、高付加価値な製品の開発など、「バイオものづくり」を支える重要な担い手になりつつあります(6)。
【文化を継ぎ、未来を創る】
麹菌が「国菌」として認定された背景には、その歴史的な貢献度と、日本の食文化における不可欠な存在であるという認識があります。この認定は、単なる学術的な評価に留まらず、日本の伝統と文化を象徴する存在として、次世代へとその価値を継承していくという強いメッセージが込められています。
一方で、本稿で紹介したように、麹菌を含むコウジカビ属菌の活躍の場は食文化にとどまりません。医療、工業、環境、そして未来の食糧として注目される代替肉まで、活躍の場は益々広がっています。今後、科学技術の進歩とともに、これらの菌は、私たちの食生活だけでなく、環境問題やエネルギー問題といった、より広範な分野においても貢献する可能性を秘めています。その秘めたる力は、まだ十分に解明されていない部分も多く、今後の研究開発によって、この小さな微生物が持つ無限の可能性は、私たちの生活をより豊かで持続可能なものへと導いてくれるかもしれません。
【参考】
(1) 秋山裕一 (2006) 近代日本の創造史 第一巻 p29-34.
DOI: 10.11349/rcmcjs.1.29
(2) K. Abe et al. (2006) Mycopathologia 162: 143-53.
DOI: 10.1007/s11046-006-0049-2
(3) B. T. Hoa & P. V. Hung (2013) International Food Research Journal 20: 3269-74.
http://ifrj.upm.edu.my/ifrj-2013-20-issue-6.html
(4) 緒方幹男 (1959) 日本釀造協會雜誌 54巻1号 p50-48.
DOI: 10.6013/jbrewsocjapan1915.54.50
(5) M. Machida et al. (2005) Nature 438: 1157-61.
DOI: 10.1038/nature04300
(6) Z. Sun et al. (2024) J Fungi 10: 248.
DOI: 10.3390/jof10040248
3.
微生物あれこれ(66)
油脂酵母Lipomyces属の研究開発動向
(山崎 敦史)
近年、油糧(ゆりょう)微生物の基礎研究や応用研究が進むなかで、得られた知見を実際の製品開発につなげる取り組みが各地で始まっています。ここでは、油脂酵母をめぐる研究開発がどのように展開してきたのかを概観します。
油脂酵母Lipomyces属についてはメールマガジン第16号(2012年)、第60号(2019年)でも取り上げてきましたが、その後、国内外での研究開発の加速が一層顕著になってきました。油脂は、植物や動物に由来する脂肪酸とグリセリンがエステル結合した中性脂肪を主成分とし、主要な生産物としてパーム油、大豆油、なたね油等があります。これらは食品、洗剤・石鹸・香粧品に加え、バイオ燃料を含む油脂化成品といった形で幅広い産業分野に利用されており、今後も需要の拡大が見込まれます。
なかでもパーム油は世界で最も生産量の多い植物油脂ですが、アブラ椰子(やし)農園の開発に伴う森林伐採や環境破壊、農園の運営における人権問題(強制労働や児童労働など)が深刻な課題となっています。このため、2004年には、「持続可能なパーム油のための円卓会議(Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO)」が設立され、持続可能なパーム油の生産と利用を推進する認証制度が導入されました。しかし、欧州では、燃料利用の観点からパーム油は依然としてハイリスクと評価がされています(1)。
このように、パーム油は多くの課題を抱える一方、今後も植物油脂のニーズは増加すると予想されます。油糧微生物が生産する油脂の脂肪酸組成はパーム油に類似しているため、代替資源としての利用が期待されています。このような背景から、海外では油脂酵母を含む油糧微生物を用いた油脂生産に取り組むスタートアップ企業(Zero Acre Farms [米国]、C16 Biosciences [米国]、NoPalm Ingredients [和蘭]、Clean Food Group [英国]等)が次々と誕生し、活発な研究開発活動が進められています。
国内においても、政府の研究開発プロジェクトのもとで微生物による油脂生産技術の開発が進められています。例えば、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」事業(2020年度~2026年度)や「バイオものづくり革命推進基金事業」(2023年度~2032年度、予算総額 約3000億円)です。新潟薬科大学の研究グループでは、2022年、油脂酵母を用いて世界トップレベルのパーム油代替油脂の生産(98 g/L)に成功しました(2)。さらに翌2023年には、Lipomyces starkeyiにおけるTAG合成を調節するタンパク質LsSpt23pに関する論文も発表され(3)、国内研究のレベルの高さが伺えます。
一方米国では、2024年に米国エネルギー省(DOE)エネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)バイオエネルギー技術室(BETO)の助成を受けたAgile Biofoundryプロジェクトから、Lipomyces属26株のゲノム解析や代謝解析を行い、さらにL. starkeyiのゲノムスケール代謝モデル(genome-scale metabolic model, GSM)を構築したという論文が発表されました(4)。このモデルにより、多様な原料を利用した効率的な油脂生産の代謝メカニズムの理解が進み、今後の有用株の育種や生産プロセス最適化への応用が期待されます。また、この研究プロジェクトは、米国においても油脂酵母を活用したバイオマニュファクチャリング研究が国主導で進められていることを示しています。
以上のように油脂酵母に関する研究開発は国内外で加速しており、経済安全保障や資源循環の観点からも、日本における今後の取り組みのさらなる進展が望まれます。
【参考】
(1) 農林水産省『令和3年度 「持続可能性に配慮した原材料調達」に関する認証システムの調査・分析委託事業報告書 2.2. パーム油の持続可能性に関する認証システムの概要』
https://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/tokutei_keihi/seika_R03/attach/pdf/itaku_R03_ippan-701.pdf (2) NEDO ニュースリリース「油脂酵母からのパーム油代替油脂で世界トップレベルの生産量(98 g/L)を実現」
(3) H. Takaku et al. (2023). Appl Microbiol Biotechnol. 107: 1269-1284.
DOI: 10.1007/s00253-023-12361-2
(4) J.J. Czajka et al. (2024). Front Bioeng Biotechnol. 12: e1356551.
DOI: 10.3389/fbioe.2024.1356551
4.
DBRP(生物資源データプラットフォーム)
~更新情報のお知らせ~
あいち産業科学技術総合センター食品工業技術センターが分離、育種、選抜した有用微生物をDBRP上で公開しました。今回公開されたのは、清酒製造などに利用可能な酵母です。近年、消費者の清酒に対する嗜好が多様化していることを受け、同センターではシンクロトロン光などの変異原を用いた育種を進めてきました。その結果、以下のような特徴を持つ酵母株が得られています。
・尿素非産生株:安全性の向上に寄与
・リンゴ様香高産生株:フルーティーな香りを強調
・高香気成分産生株:同センター所有の従来株に比べ、カプロン酸エチルや酢酸イソアミルなどの香気成分を多く生成
清酒製造向け以外にも、発酵茶飲料向けの株の情報も掲載しています。ご興味のある方は、下記リンクよりお申し込み方法やご利用条件をご確認ください。
【あいち産業科学技術総合センター食品工業技術センター保有微生物資源 コレクション情報】
https://www.nite.go.jp/nbrc/dbrp/dataview?dataId=COLL0001300000001
5.
NITE講座開催のご案内
「微生物の同定や解析のための基盤技術-MALDI-TOF MSを用いた
微生物同定と、マイクロバイオーム解析の精度向上-」
微生物研究を支える基盤技術を紹介するNITE講座を開催します。
今回のテーマは、「MALDI-TOF MSを用いた微生物同定」と「微生物カクテルによるマイクロバイオーム解析の精度向上」です。
MALDI-TOF MSによる微生物の迅速同定を導入しようとお考えの皆様や、NBRC微生物カクテルを用いたマイクロバイオーム解析の精度向上に関心のある皆様のご参加をお待ちしております。
セミナー概要
日時:2025年11月28日(金)13:30~15:30(予定)
開催形式:オンラインセミナー(Teamsウェビナー)
定員(先着順):1,000名
参加費:無料
申込方法:後日、NITEウェブサイトにて掲載公開予定
今回のテーマは、「MALDI-TOF MSを用いた微生物同定」と「微生物カクテルによるマイクロバイオーム解析の精度向上」です。
MALDI-TOF MSによる微生物の迅速同定を導入しようとお考えの皆様や、NBRC微生物カクテルを用いたマイクロバイオーム解析の精度向上に関心のある皆様のご参加をお待ちしております。
セミナー概要
日時:2025年11月28日(金)13:30~15:30(予定)
開催形式:オンラインセミナー(Teamsウェビナー)
定員(先着順):1,000名
参加費:無料
申込方法:後日、NITEウェブサイトにて掲載公開予定
6.
2025年度JACセミナー参加者募集のお知らせ
NITEが参加している国内5つの認定機関による「日本認定機関協議会(JAC)」主催のセミナーを、以下のとおり開催します。
今年は「世界認定推進の日」のテーマ 「認定、それは中小企業の発展に力を与える」 に沿って、生成AI、SAF原料リサイクル、大阪・関西万博、JCSS質量分野などに関連する講演をお届けします。認定や関連分野に関心のある方は、ぜひご参加ください。
開催概要
日時:2025年10月3日(金)12:50~16:30
開催形態:ハイブリッド(会場+オンライン)
定員:会場80名(オンライン参加は無制限)
参加費:無料
詳細:https://www.nite.go.jp/iajapan/jac/information/2025_jacseminar.html
今年は「世界認定推進の日」のテーマ 「認定、それは中小企業の発展に力を与える」 に沿って、生成AI、SAF原料リサイクル、大阪・関西万博、JCSS質量分野などに関連する講演をお届けします。認定や関連分野に関心のある方は、ぜひご参加ください。
開催概要
日時:2025年10月3日(金)12:50~16:30
開催形態:ハイブリッド(会場+オンライン)
定員:会場80名(オンライン参加は無制限)
参加費:無料
詳細:https://www.nite.go.jp/iajapan/jac/information/2025_jacseminar.html
7.
NBRCが展示、発表等を行うイベントについて
以下のイベントにて出展、講演、発表等を行います。ぜひご参加ください。
京都バイオ計測センター研究交流発表会2025
~AlphaFoldから始める、実験研究者のためのバイオインフォマティクス~
日時:2025年10月2日(木)
会場:三洋化成工業株式会社 桂研究所1階ホール(京都市西京区御陵大原1-40)
URL:https://tc-kyoto.or.jp/kist-bic/news/kenkyukouryuhappyou2025.html
NITEの参加形態:講演
BioJapan 2025
日時:2025年10月8日(水)~10日(金)
会場:パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)
URL:https://jcd-expo.jp/jp/
NITEの参加形態:ブース出展、ポスター発表(NEDOブース)
千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議
令和7年度バイオものづくりセミナー
日時:2025年10月20日(月)
会場:ペリエホール Room A(千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ7F)
URL:https://www.kazusa.or.jp/workshops/cbln/
NITEの参加形態:講演
ビジネスマッチ東北
日時:2025年11月13日(木)
会場:夢メッセみやぎ(宮城県仙台市宮城野区港3-1-7)
URL:https://www.bmtohoku.jp/
NITEの参加形態:ブース出展
京都バイオ計測センター研究交流発表会2025
~AlphaFoldから始める、実験研究者のためのバイオインフォマティクス~
日時:2025年10月2日(木)
会場:三洋化成工業株式会社 桂研究所1階ホール(京都市西京区御陵大原1-40)
URL:https://tc-kyoto.or.jp/kist-bic/news/kenkyukouryuhappyou2025.html
NITEの参加形態:講演
BioJapan 2025
日時:2025年10月8日(水)~10日(金)
会場:パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)
URL:https://jcd-expo.jp/jp/
NITEの参加形態:ブース出展、ポスター発表(NEDOブース)
千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議
令和7年度バイオものづくりセミナー
日時:2025年10月20日(月)
会場:ペリエホール Room A(千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ7F)
URL:https://www.kazusa.or.jp/workshops/cbln/
NITEの参加形態:講演
ビジネスマッチ東北
日時:2025年11月13日(木)
会場:夢メッセみやぎ(宮城県仙台市宮城野区港3-1-7)
URL:https://www.bmtohoku.jp/
NITEの参加形態:ブース出展
編集後記
少しずつ暑さも落ち着き、秋らしい季節になってきました。スポーツの秋、読書の秋など色々ありますが、皆様はどのような秋をお過ごしでしょうか?秋は葡萄や梨、秋刀魚などのおいしい旬の食べ物が多いので、私は食欲の秋を楽しみたいと考えています!
今号では、日本の食や産業を支える微生物として、「びせいぶつ学習帳」での麹菌の紹介や、DBRPに公開された清酒製造などに利用可能な酵母の紹介をさせていただきました。その他、油脂生産酵母の研究開発の動向についてもまとめておりますので、よろしければご一読いただけますと幸いです。次号も、NBRCならではの話題をお届けします!(KM)
少しずつ暑さも落ち着き、秋らしい季節になってきました。スポーツの秋、読書の秋など色々ありますが、皆様はどのような秋をお過ごしでしょうか?秋は葡萄や梨、秋刀魚などのおいしい旬の食べ物が多いので、私は食欲の秋を楽しみたいと考えています!
今号では、日本の食や産業を支える微生物として、「びせいぶつ学習帳」での麹菌の紹介や、DBRPに公開された清酒製造などに利用可能な酵母の紹介をさせていただきました。その他、油脂生産酵母の研究開発の動向についてもまとめておりますので、よろしければご一読いただけますと幸いです。次号も、NBRCならではの話題をお届けします!(KM)
・画像付きのバックナンバーを以下のサイトに掲載しております。受信アドレス変更、受信停止も以下のサイトからお手続きいただけます。
NBRCニュースバックナンバー
・NBRCニュースは配信登録いただいたメールアドレスにお送りしております。万が一間違えて配信されておりましたら、お手数ですが、以下のアドレスにご連絡ください。
・ご質問、転載のご要望など、NBRCニュースについてのお問い合わせは、以下のアドレスにご連絡ください。
・掲載内容を許可なく複製・転載することを禁止します。
・NBRCニュースは偶数月の1日(休日の場合はその前後)に配信します。次号(第96号)は2025年12月初旬の配信を予定しています。
編集・発行
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)バイオテクノロジーセンター(NBRC)
NBRCニュース編集局(nbrcnews【@】nite.go.jp)
(メールを送信される際は@前後の【】を取ってご利用ください)
NBRCニュースバックナンバー
・NBRCニュースは配信登録いただいたメールアドレスにお送りしております。万が一間違えて配信されておりましたら、お手数ですが、以下のアドレスにご連絡ください。
・ご質問、転載のご要望など、NBRCニュースについてのお問い合わせは、以下のアドレスにご連絡ください。
・掲載内容を許可なく複製・転載することを禁止します。
・NBRCニュースは偶数月の1日(休日の場合はその前後)に配信します。次号(第96号)は2025年12月初旬の配信を予定しています。
編集・発行
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)バイオテクノロジーセンター(NBRC)
NBRCニュース編集局(nbrcnews【@】nite.go.jp)
(メールを送信される際は@前後の【】を取ってご利用ください)
お問い合わせ
-
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします) -
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
お問い合わせフォームへ